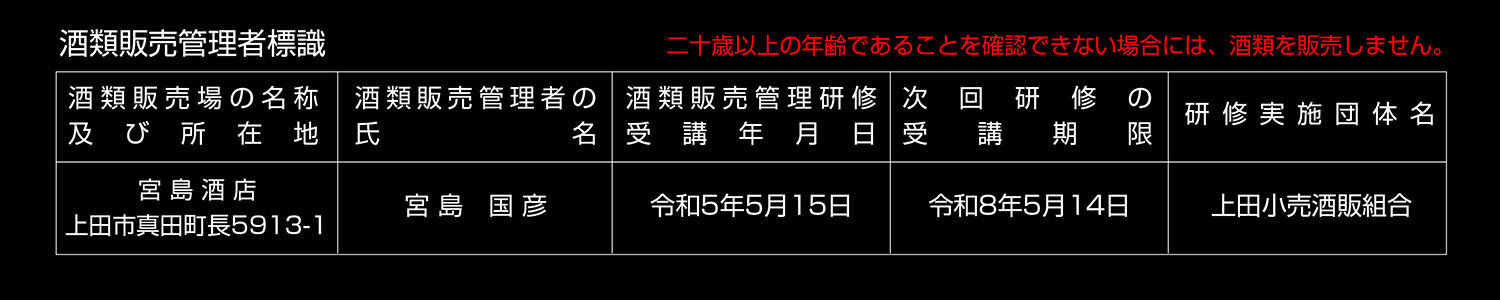ご挨拶
この度当店は、2023年11月をもちまして創業100周年を迎えさせていただきました。
同時に「信州産地酒専門店」として25周年を迎えさせていただきました。
これもお客様をはじめ大切な商品を製造下さっている酒造メーカー様、関係者様皆様のお蔭と心より感謝申し上げます。
創業は1923年、曽祖父(宮島國一)が、商店を構えるところから始まります。
次いで祖父(貫五)が後継し、生鮮食品も扱うミニスーパーの様な形態での商売でした。
父(政雄)が1985年に現在の店舗に移転し、当時ではまだ珍しいコンビニ形態の店舗としてスタートしました。
1998年、信州長野県産の地酒専門店で展開する決意をし、2000年に店舗改装(2017年再改装)をし、現在に至ります。
当時は不安なままのスタートでしたが、「信州の地酒は美味しい上に、更にもっと美味しくなる!」を信じて参りました。
今、振り返りますと、信じてやって来て良かった!と、心から感謝の気持ちでいっぱいです。
そこで創業100周年への感謝の気持ちを形にしたいと考え、お客様やお取引先様をお呼びしての『イベント事業』を考えて居りましたが、結果的には、創業100周年記念の『記念酒発売企画』と、信州地酒の魅力を更に積極的にお伝えする為の、『魅力発信企画』に至りました。
『記念酒発売企画』につきまして
信州の酒蔵数は、全国2位ですが、女性杜氏数は、全国1位(暫定)を誇る長野県であります。
その女性杜氏が醸す作品を、全酒造メーカー様から直接取引をさせていただけているのは、全国で当店だけであると言う実績と、日本酒業界で多くの女性が活躍されている事への、更なるエールを、お客様にお届けしたいと考えました。
また女性杜氏7名の「7」は、コロナ禍や自然災害・紛争などから、平和に向かっての『(七色の)虹の架け橋』をイメージ出来、まさに100周年のテーマとしてピッタリであると自負しております。
本作のリリースにつきましては、ホームページ上の「特設サイト」でご案内させていただきます。
(お申込みは終了しました)
『信州地酒魅力発信企画』につきまして
100周年を機に、信州地酒の更なる魅力を伝えるべく、店主自らが長野県内では3人目となる「日本酒学講師」(日本酒サービス研究会「SSI」認定資格)を取得させていただきました。
こちらは、信州地酒の素晴らしさお伝え出来る企画を、店舗とは別に展開して参る所存ですので、是非ご活用ください。
こちらも当店ホームページ上の「特設サイト」で発信して参ります。
結びに、100周年を迎えさせていただいた以降も変わらぬご愛顧、ご指導を宜しくお願い申し上げ、乱文ながら、この度の御挨拶とさせていただきます。
まことにありがとうございます。
地酒屋宮島
ご祝儀その他のお心遣いは、慎んでご辞退申し上げます。
「日本酒学講師」日本酒サービス研究会(SSI)認定資格

地酒屋の店主の他にこんな事もやってます
(信州の地酒で「何か」ございましたらご相談ください)
◎店主プロフィール
- 「日本酒学講師」・「きき酒師」 料飲専門家団体連合会(FBO公認)
- 長野県おいしい信州ふーど公使(日本酒)
- FMとうみ「はれラジ」 地酒番組パーソナリティ(2021年~)
◎地酒講義
- 信州大学 繊維学部
- 長野大学
- 日本ソムリエ協会 長野支部 ほか
◎ほか
- しなの鉄道「ろくもん」日本酒列車 監修
- SBCラジオ 地酒コーナー 指南役(~2018)
- 県内酒造メーカー様への商品プロモーションアドバイス
- 地酒イベント「信州のIPPON!」イベントディレクター
資格取得のご挨拶
(以下:当方が担当させていただいている地元ラジオ番組で発表した内容の一部を抜粋しています)
この度、地酒屋宮島 店主が、この創業100周年をきっかけに、年齢も(当時)55歳で「なんでもGO!GO!(55)」と言うことで、この年で「資格試験」にチャレンジしたお話しと、そのご報告をさせていただきます。
その「チャレンジ」とは、自身の仕事でもある、日本酒の資格試験へのチャレンジのお話しです。
わたくし、この仕事を始める時に取得した資格が、「きき酒師」という日本酒資格で、料飲専門家団体連合会 通称:FBO(お酒部門:SSI)が主催する、国内で最も有名な日本酒資格でした。
一次試験の筆記試験と二次試験の実技両方をクリアしてきき酒師としての資格がいただけるというもので、現在、国内外に約40,000人余の「きき酒師」さんがいるそうです。
今回わたくしが目指した資格は、きき酒師の上位資格で「日本酒学講師」という、簡単に言うと、「日本酒の先生的な資格」でした。
要は、日本酒の知識や情報を、多くの方にきちんとお伝えする資格となります。
この資格を取りますと、「日本酒学講師」自身が日本酒セミナーを独自開催出来るようになり、ご参加いただいた方には、SSIが認める「日本酒ナビゲーター」という資格をお与えすることができるようになります。
信州の地酒だけの専門店としましては、信州の地酒の様々なコトを、きちんとお伝えする仕事が益々重要だと考えていましたが、ここ数年チャレンジするきっかけと勇気が無かったんです。
こんな資格をいつか取れたらイイな~!なんて遠くの理想の話しにしていました。
が、具体的に動き出したのが2023年お正月のことでした。
2023年の11月が当店創業100周年を気にし出しており、自分自身にも起爆剤的なモノが何かないかと思っていたのがずっとありまして、お正月って何か決めるタイミングには良いな!と思いまして。
まずは意を決して、3月に開催される「日本酒学講師 研修会」に申し込みをしました。
人様にお伝えすることの大切さや難しさは、経験してみないと分かりません。
が、地酒の魅力をしっかりとお伝えするには、やはり自分なりに更なるスキルアップが必要であると思ったからなんです。
さてこの研修ですが、3日間に及ぶ研修で、最終日は少し早く終わりますが、3日間、朝9時から夜9時30分まで缶詰めの、ハードなモノでした。
受講生は、30代~40代が多く、女性が半分近くいらっしゃいました。
そしてなんと四分の一程が、アメリカ・台湾・韓国・中国・オーストラリアなどからの外国の方で、「日本酒文化」が海外からは非常に高い注目を得ている事を実感しました。
受講内容は、「日本酒学講師」は、人様にお伝えする資格ですので、専門知識以外のコトも多く学ぶ研修となりました。
講師というだけあって、お教えするスキル、インストラクションスキルと、多くの人との交流を持つ点から、コミュニケーションスキルを、更には自身の日本酒セミナーを組み立てるので、プランニングスキルなどを3日間かけて学びました。
具体的には、ビジネスマナー・礼儀作法(プロトコール)・ボイストレーニングなどを勉強した後、受講生や講師先生全員の前で、原稿なしでの1分間の自己アピールスピーチを行います。
すごい人は、この1分間の中で、複数回の拍手をもらったりした方も居て、びっくりしました。
なんとか3日間に及ぶ研修を終えますが、約2カ月後に試験があります。
この試験が、
一次試験 筆記=講師としてのスキルを試され
二次試験 筆記=自分で計画した日本酒セミナーのプランを試され
三次試験 筆記=日本酒と本格焼酎の更なる知識を問われ
四次試験 面接(オーディション)=受講生の人数と会場の規模が想定された中で実際に「日本酒セミナー」を開く
と、かなりハードなモノでして、念入りな準備が必要なのが直ぐに分かりました。
試験結果発表までは約1カ月待ちます。
そして一か月後。
試験結果発表通知が届きました。
結果は、なんと!合格しておりました。
後日FBOに問い合わせたところ、国内外で約500名余の「日本酒学講師」がいらっしゃり、長野県では、わたくしで3人目の認定となるそうです。
2023年8月1日から「日本酒学講師」として認定され、地酒屋の店主の他に、もう一つのお仕事をさせていただけることとなります。
認定書などは8月下旬に届きますので、実質的には9月からのスタートとなります。
日本酒や地酒にご興味のある方、また飲食店様などでのスタッフへの日本酒のスキルアップなどのビジネスシーンで、是非この地酒屋宮島の「日本酒セミナー」をご活用ください。
また「日本酒セミナー」までは受講する気持ちにはなれないけど、こんな事を聞いてみたい!と、お考えの方は、どんな些細な事でも結構ですので、遠慮なくお問い合わせください。
お問い合わせやお申込みは、「セミナー・イベント紹介ページ」をご利用ください。
結びに
世の中には上には上があって、日本酒・焼酎・ワインなどの難しい資格を複数持たれて、幅広い分野で世界的にご活躍されている方がたくさんいらっしゃいますし、すごいな~と憧れる事が今でもたくさんあります。
でも自らの立ち位置で、信州の地酒の為に、それを更によろこんでくださる方のために、この創業100周年を機に、「信州地酒の伝道師」として一生懸命頑張りたいと思います。
多くの皆さまのお蔭で、受験する勇気ときっかけを与えてくださったことに感謝して、この度の御礼とご報告にさせていただきます。
日本酒学講師
地酒屋宮島 代表 宮島国彦
セミナー・イベント紹介
◎告知(地酒イベント紹介)
おかげさまでこちらのイベントは大盛況にて終了しました
長野県外のお酒関連イベントで出品数最大規模の試飲イベント開催決定!
新感覚の試飲イベント
「信州のIPPON! 〜長野県の日本酒&ワインと出会う1日〜」
詳細発表
2023年11月18日(土)12:00~18:00まで、業界初となる大規模な信州地酒(日本酒・ワイン)の試飲イベントを東京都内で開催します。
会場は今年開業した、東京駅前の新商業施設「東京ミッドタウン八重洲」。
主催は、街の酒屋(酒販店)の公認団体である長野県小売酒販組合連合会です。
こちらが主催になることで、公式に長野県の日本酒とワインのコラボイベントが初めて長野県外で開催出来る運びとなりました。
さて長野県は、酒蔵の数(計80場)とワイナリーの数(71場)が共に全国第2位と「日本酒とワイン」の県です(2021年時点)。
その中でも今回の参加酒造メーカーは、日本酒は「信州のお酒の試飲イベント」としては出品数が最大と言われる地元長野開催の「YOMOYAMA長野」(主催:長野県酒造組合)の58場を超え62場(出品数)に。
※女性杜氏 全7蔵・SAKU13 全13蔵・59醸会 全5蔵なども出品決定!
※「信州のIPPON」当日に、新作発表する蔵も登場!
ワイナリーも老舗から新進気鋭まで、県内全てのワインバレーから16場の参加が叶いました。(いずれにしても過去最大規模となります)
内容は、参加メーカーそれぞれが自慢の1銘柄(1本:IPPON)を持ち寄り、自由に試飲をしていただく「試飲イベント」に加え、その造り手たちと語り合うことが出来る「交流イベント」、長野県の日本酒やワインの魅力を語る「トークセッション」、長野県産の日本酒やワインとのペアリングを楽しんでいただく「フードコーナー」など、多彩なコンテンツで長野県の日本酒、ワインの魅力を知っていただきます。
それでは詳細を発表します!
※画像クリックで拡大できます(PDF)。
参加酒造メーカー【決定版】はこちら(PDF)
- 開催日・会場
開催日時: 令和5年11月18日(土) 12:00〜18:00
会 場: 東京ミッドタウン八重洲カンファレンス 4F・5F
(東京都中央区八重洲2-2-1 「受付:4F(エントランス)」)
- 「試飲会」チケット
チケット: イープラスにて販売中
価 格: 4,000円(税込) ※イープラスの各種発券手数料等別
内 訳: 試飲会参加券+会場内有料飲食に使用出来る1,000円分のコイン付
- イベントコンテンツ
■長野県内の酒蔵・ワイナリー自慢の1作品(IPPON)を試飲出来る「試飲コーナー」
(日本酒62場、ワイナリー16場 計78の酒造メーカーが参加決定)
■酒蔵・ワイナリーの造り手とお酒を飲みながら語り合える「交流コーナー(有料)」
(日本酒17場、ワイナリー10場 計27の酒造メーカーが参加決定)
■長野県の日本酒、ワインの魅力を伝える「トークセッション」
■長野県産の日本酒、ワインとのペアリングを楽しむ「フードコーナー(有料)」
- 「信州のIPPON!」の魅力とは! (ここがポイント!)
その1 東京駅前の最新施設「東京ミッドタウン八重洲」の4・5階 2フロアでの開催
東京駅直結徒歩2分という申し分のない立地に今年4月にオープンしたばかりの大型複合施設「東京ミッドタウン八重洲」。
その4・5階は都市と地域のイノベーション起点として、その「場所」と地域や産業分野を超えた共創の「機会」を提供するという理念から「イノベーションフィールド」と名付けられていますが、その理念と本イベントの趣旨が合致し、開催会場として選定させていただきました。
東京の中心地にある最新施設のお洒落な空間で長野県の日本酒・ワインを味わい、楽しんでいただくことで、長野県の日本酒・ワインの魅力を知っていただくための、劇場で言う「二幕構成」で4階と5階にイベントコンテンツを分けた開催をします。
その2 4階 試飲コーナー イベントタイトル「信州のIPPON!」の本当の意味とは!
各地で試飲イベントが開催されていますが、1メーカー当たりの出品種類の多さやメーカーの引用温度帯にバラツキがあることで、それぞれメーカーのお酒を、同じ温度帯で比較して楽しむという点では、差違が生じていました。
今回のイベントは、11月中旬の屋内開催という気候を活かし、「常温提供」を大きなポイントとし、さらに1メーカー1種類で、希望小売価格の上限を設定することで、(その価格帯までの)各メーカーの「柱商品=IPPON」を同じ温度帯で口に出来る、めったにないチャンスを提供します。
また、試飲環境も統一するため、酒造メーカーの方も試飲イベント会場にはおらず、共通のポアラー(注ぎ器)を用意して、来場者が自らセルフで注ぎ、試飲をしていただけるようにし、試飲酒とメーカーの情報は各参加メーカー毎のブースに用意したQRコードから情報を取得していただけるようにします。
その3 5階 交流コーナー、信州のIPPON!と食のペアリング&トークショー
「試飲コーナー」で口に合ったお酒が見つかったら、食事と合わせてみたくなったり、メーカーの方と直接話をしてみたくなったりするはず。
そこでもう少し「長野県の日本酒とワイン」に触れてみたいという方のためのイベントを5階で開催します。(一部、チケット代以外の費用が必要となります)
(1) 交流コーナー
多くの酒造メーカーが「交流コーナー」でお待ちしています。
こちらではキャッシュ・オン・デリバリーで参加メーカーのお酒を楽しみながら、酒造メーカーの方との交流をしていただくことが出来ます。
(2) フードコーナー
長野県はお酒以外にも、お味噌や醤油、漬物、チーズなど数多くの発酵食の生産が盛んですが、日本酒・ワインにペアリングする食材として発酵食は最高の食材の一つです。
そこで今回のイベント用に発酵食を中心にしたフードメニューを用意し、ペアリングを楽しんでいただきます。(こちらのコーナーもキャッシュ・オン・デリバリーとなります)
(3) トークショー
長野県の日本酒・ワインについて、その魅力をより知っていただくため、著名杜氏や長野県のワイン業界の中心人物などにご登壇いただき、トークショーも開催します。
長野県の日本酒・ワインとお食事を楽しみながら、信州のお酒に関わる素晴らしい「人」にも出会っていって下さい。
■「世界一の日本酒を生んだ杜氏2人のスペシャルトークセッション」(14:00〜15:00)
出演:湯川酒造店 湯川慎一氏、諏訪御湖鶴酒造場 竹内重彦氏、SAKE TIMES編集長 小池潤氏
■「長野ワインの未来を語る!」(16:00〜17:00)
出演:信州ワインバレー構想推進協議会会長 成澤篤人氏、同副会長 花岡純也氏
ほか NewsPicks主催トークセッション(12:30〜13:30)
- ボランティア募集
本イベントでは運営に携わっていただくボランティアも募集しています。
日本酒やワインに興味・関心のある方、長野県が好きな方などのご参加をお待ちしています。(ボランティア情報サイト「activo」(アクティボ)にて募集中)
以上、ご案内となります。
「信州のIPPON!」は、コロナ禍による外出の自粛や消費の停滞で、信州の地酒業界も大打撃を受けましたが、「地酒復興」を首都圏でも形にすべく、長野県内の街の酒屋が全力で臨むイベントです。
飲食店や小売店などお酒業界の皆さまをはじめ、皆さまのファンの方々や知人友人、ご家族など多くの方のご来場をお待ちしております。
結びに。。
今回この企画にコーディネート担当として、立ち上げの段階から関わらせていただいた、わたくし自身も、信州の地酒を好立地でスタイリッシュに表現できる機会に感謝しながら、より多くの皆様に信州の地酒の魅力お伝えするべく、発信力や影響力のある皆様には勿論、SNSなどを通じ、できるだけ多くの皆様に積極的にダイレクトにご連絡・ご案内をさせていただきたいと存じます。
(お送りした皆様には、突然のお誘いで失礼且つまた、お手数かとは存じますが、ご参加やご拡散をお願い出来れば幸甚と存じます。)
是非ご理解とご協力を何卒宜しくお願い申し上げます!
100周年記念商品
創業100周年(地酒専門店25周年)記念酒について
こちらのお申込みは終了しました
信州の酒蔵数は、全国2位ですが、女性杜氏の数は、全国1位を誇る長野県であります。
その女性杜氏が醸す作品を、全酒造メーカーから直接取引をさせていただけているのは、全国で当店だけであると言う実績と、日本酒業界で多くの女性が活躍されている事への、更なるエールを、お客様にお届けしたいと考えました。
また女性杜氏7名の「7」は、コロナ禍や自然災害・紛争などから、平和に向かっての『(七色の)虹の架け橋』をイメージ出来、まさに100周年のテーマとして、ピッタリであると自負しております。
そこでこの度、長野県内七蔵の女性杜氏の作品を、同規格の300ml瓶に詰め、統一デザイン化した「地酒屋宮島100周年記念パッケージ」として発売します。
内容は以下となります。
今回の商品のご紹介(ボトル・ラベルデザイン)はこちら
(こちらを1つの箱にお入れして販売いたします)

「100周年記念酒(7人の女性杜氏)担当蔵」
デザインは、各蔵元のブランドストーリーや銘柄からのイメージを大切に作成しました。
また、信州の名産のひとつでもある「水引き」をデザイン上で同じ高さにすることで、お客様をはじめ、7名の女性杜氏、酒造メーカーと当店が「繋がっている」事を表現しました。
※酒造会社名50音順(法人格・敬称略)と出品銘柄・杜氏名(敬称略)
・大塚酒造 「浅間嶽」 大塚白実
・岡崎酒造 「信州亀齢」 岡崎美都里
・尾澤酒造場 「十九」 尾澤美由紀
・高天酒造 「高天」 高橋美絵
・酒千蔵野 「川中島幻舞」 千野麻里子
・高沢酒造 「豊賀」 高沢賀代子
・若林醸造 「つきよしの」 若林真実
※詳細は、商品内にオリジナルリーフレットをお入れします
- 数量:(100周年だけに) 100セット限定
- 価格:(100周年だけに) 10,000円(税別) <11,000円(税込)>
- 販売:抽選制のみ
お申し込みは、当店ホームページ内のメールフォームのみで受け付けます。
直接お申込みが出来るよう、最下段にリンクを貼らせていただきました。(受付終了後 削除)
※必ず以下をご一読の上、エントリーください。
※20歳以上の年齢を確認出来ない場合にはエントリー出来ません。
(エントリーの際、年齢確認をさせていただきます)
●第一次抽選:「信州地酒頒布会2023」会員様 先行受付
※「信州地酒頒布会2023」会員様には同じ情報が今月の頒布会と一緒に入ります。
★エントリー期間 10月20日~11月5日 (先着順ではございません!)
一般のお客様 11月6日~11月10日
※期間外のエントリーは対象外となります!
※1会員様1回まで(複数個口の会員様はその口数)のエントリー
★抽選結果発表(11月中に当選者様にメールにて直接ご連絡します)
※複数個口の会員様が複数当選された場合のみ1口に調整致します。
●第二次抽選:一般のお客様
★エントリー期間 11月6日~11月10日 (先着順ではございません!)
※期間外のエントリーは対象外となります!
※1グループ(家族・会社・団体含む)様 1回までのエントリー
★抽選結果発表(11月中に当選者様にメールにて直接ご連絡します)
●商品引渡:
★店頭引渡しの方:11月23日~11月30日の間
★発送引渡しの方:12月2日~12月10日の間
※期間内に店頭、若しくは発送での受け渡しの完了が可能な方に限ります。
※期間内に受け渡しが出来ない場合は、無効とさせていただきます。
◎もうひとつの記念品
こちらのご予約は終了しました
当店では、多くのお客様へ出来るだけ多くの感謝の気持ちをお伝えしたく、実はもう一作品のご用意がございます。
その「もうひとつの記念品」が、「宮島盃(ミヤジマサカズキ)」です。
製作は同じ真田町在住で、インスタグラムのフォロワー数が30万人を超える、
『陶芸家:阿部春弥さんの当店ロゴ入りオリジナル盃』を販売させていただきます。
今回の商品のご紹介はこちら(画像はイメージとなります)


※こちらは上記抽選で当選されなかった方を優先します。
- 数量:(100周年だけに) 100個限定
- 価格:(上限2個まで) 1個 1,500円(税別) <1,650円(税込)>
- 販売:12月15日 開店時~(以下のご予約分で完売の場合は発売致しません)
- 予約:12月1日~12月10日(先着順:予告なく完売となる場合があります)
※予約完売の際は、こちらに発表させていただきます。
ご予約は、当店ホームページ内のメールフォームのみ(12月1日~12月10日)で受け付けます。
●ご注意ください!
- 今回のエントリーは、メールのみとなります。
エントリー終了の返信メールはしませんのでご了承ください。
当選メールが受信拒否にならないような設定をお願いします。 - 本件で予約者がメールの送受信が出来ない場合は、予約とはなりません。
- 本品のオークションサイトへの出品や転売は、固くお断りします。
- 本件に関する、メーカーへのお問い合わせ、ご意見などはお控えください。
- 予約された方のキャンセルは出来ません。